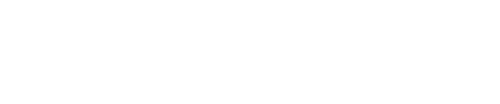大会概要
- 大会名称
- 第101回天皇杯・第92回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会
・ファーストラウンド
・セカンドラウンド
・ファイナルラウンド
- 主催
- ≪ファーストラウンド~ファイナルラウンド≫
公益財団法人日本バスケットボール協会
≪ファーストラウンド~セカンドラウンド≫
当該都道府県バスケットボール協会
≪セカンドラウンド≫
当該ブロックバスケットボール協会
- 共催
- ≪ファーストラウンド~ファイナルラウンド≫
共同通信社
≪ファーストラウンド~ファイナルラウンド2回戦≫
北海道新聞社、東奥日報社、デーリー東北新聞社、岩手日報社、河北新報社、秋田魁新報社、
山形新聞社、福島民報社、福島民友新聞社、茨城新聞社、下野新聞社、上毛新聞社、埼玉新聞社、
千葉日報社、東京新聞、神奈川新聞社、新潟日報社、北日本新聞社、北國新聞社、福井新聞社、
山梨日日新聞社、信濃毎日新聞社、岐阜新聞社、静岡新聞社、中日新聞社、京都新聞社、産業経済新聞社、
神戸新聞社、奈良新聞社、新日本海新聞社、山陰中央新報社、山陽新聞社、中国新聞社、徳島新聞社、
四国新聞社、愛媛新聞社、高知新聞社、西日本新聞社、佐賀新聞社、長崎新聞社、熊本日日新聞社、
大分合同新聞社、宮崎日日新聞社、南日本新聞社、琉球新報社、沖縄タイムス社
- 主管
- ≪ファーストラウンド~セカンドラウンド≫
当該都道府県バスケットボール協会
≪セカンドラウンド≫
当該ブロックバスケットボール協会
≪ファイナルラウンド≫
公益財団法人日本バスケットボール協会
- 後援
- NHK
- 協賛
- 三井不動産株式会社
ジョーダン ブランド
株式会社モルテン
三井住友信託銀行株式会社
ソフトバンク株式会社
- 日程
- ≪ファーストラウンド≫
原則、2025年8月までに開催
≪セカンドラウンド≫
原則、2025年11月までに開催
≪ファイナルラウンド≫
【皇后杯】2026年1月5日(月)~11日(日) ※7日(水)、10日(土)はレストデー
【天皇杯】2026年1月6日(火)~12日(月・祝) ※9日(金)、11日(日)はレストデー
- 会場
- ≪ファーストラウンド≫
当該都道府県会場
≪セカンドラウンド≫
当該ブロック会場
≪ファイナルラウンド≫
【皇后杯】国立代々木競技場第一体育館・第二体育館・駒沢体育館
【天皇杯】国立代々木競技場第一体育館・第二体育館
- 大会方式
- ≪ファーストラウンド≫
当該都道府県協会に選出方法を一任する。
≪セカンドラウンド~ファイナルラウンド≫
トーナメント戦によるノックアウト方式とする。
- FR組み合わせ
- ファイナルラウンドの組み合わせは、大会実施委員会の責任抽選にて抽選を行い、対戦を確定するものとする。
- 競技規則
- 各ラウンドとも開催時における最新のバスケットボール競技規則で実施する。
※現状においては 「2025バスケットボール競技規則 (Official Basketball Rules 2024)」 を最新とする。
- 出場資格(チーム)
- 2025年度において当該都道府県の下記カテゴリー・チーム区分にチーム登録されているチーム (JBA登録区分に基づく) であること。
・一般(Ⅰ種)カテゴリー
・U18カテゴリー
- 出場チーム数
- ≪ファーストラウンド≫
原則、6チーム以上として、各区分に対して出場機会を提供したうえで、当該都道府県協会にて定めること。
≪セカンドラウンド≫
原則、6チーム以上として、各区分に対して出場機会を提供したうえで、当該都道府県協会にて定めること。
≪ファイナルラウンド≫
【皇后杯】
・ブロック代表枠
原則、当該年度の11月までにブロックラウンド(9ブロック)を開催し、各ブロック1枠ずつ
・社会人推薦枠
前シーズンの成績(高松宮記念杯 全日本社会人バスケットボールプレミアムチャンピオンシップ優勝・準優勝チーム)に1枠ずつ
・大学推薦枠
前年度の全日本大学バスケットボール選手権大会優勝チームが所属する地区の当該年度の選手権大会(春季大会)上位3チームに1枠ずつ
・トップリーグ推薦枠(Wリーグ)
前シーズンの成績を基にプレミア:8枠、フューチャー:2枠
【天皇杯】
・ブロック代表枠
原則、当該年度の11月までにブロックラウンド(9ブロック)を開催し、各ブロック1枠ずつ
・社会人推薦枠
前シーズンの成績(高松宮記念杯 全日本社会人バスケットボールプレミアムチャンピオンシップ優勝チーム)に1枠
・大学推薦枠
前年度の全日本大学バスケットボール選手権大会優勝チームが所属する地区の当該年度の選手権大会(春季大会)優勝チームに1枠
・トップリーグ推薦枠(Bリーグ、B3リーグ)
前シーズンの成績を基にB1:8枠、B2:4枠、B3:1枠
- 参加資格
-
- 1. 2025年度においてJBAに選手登録された選手であること。
- 2. 外国人選手は、JBA基本規程第110条に基づいて登録された選手であること。
- 3. ※日本と在籍国間の相互免除により査証を有しない外国籍選手および観光査証により来日している外国籍選手の登録不可。
- 4. 帰化選手は満16歳となった後に国籍法に基づく帰化によって日本国籍を取得した選手であること。
- チーム編成
-
- 1. チーム編成はスタッフ9名以内、選手16名以内の計25名以内とする。
- 2. ベンチで指揮を執るコーチはJBAが定めるコーチライセンスの適用基準において必要な資格を保有していること。
- 3. 選手は、天皇杯・皇后杯を通して、大会申込み時に選択(エントリー)したチームのみとする。
※ファーストラウンド(都道府県ラウンド)で選手登録をしたチームでのみ出場ができる。
※ラウンド毎に選手登録するチームが変わることは不可とする。(同ラウンド中も変更は不可)
- 4. Bリーグ・B3リーグにおける「アジア特別枠選手」は外国籍選手とする。
- 5. Bリーグ・B3リーグにおける 「特別指定選手」 は、今年度の天皇杯(ファーストラウンド~ファイナルラウンドまで)で一度もエントリーされていない者だけが参加可能であるが、大会申込み期限までにTeam JBAにて当該チームに選手登録されている (他連盟等での選手登録がない選手である) こと。(「ユース育成特別枠」 は、Bユースに在籍中でなければならないため、参加はできない)。
- 7. 選手登録および大会エントリーができる外国籍選手数は、1チーム合計2名までとし、帰化選手は、外国籍選手とは別に1名まで選手登録できる。また、試合中同時にコート上でプレーできる外国籍選手数は、試合を通して1チーム合計1名までとする。帰化選手は、試合を通してコート上でプレーできる人数は1名までとし、常時、外国籍選手1名と同時にプレーすることができる。延長時限においても同様に取り扱う。
【違反時の対応】
規定数以上の外国籍選手が交代によりコートへ入り、再開のためにスローインを行うプレーヤー
にボールが与えられたとき、あるいは最初のフリースローでフリースローを行うプレーヤーにボール
が与えられたとき以降にそれが確認された場合は、その時点で審判員は当該チームのコーチへ
テクニカルファウルを宣告し、外国籍選手を交代させ規程数以内であることを確認した後に試合
を再開する。
- ユニフォーム規定
-
- 1. JBAユニフォーム規則に準ずる。
- 2. その他の身につけることができるもの・できないものは競技規則第4条に準ずる。
- 3. ユニフォーム広告についても原則としてJBAユニフォーム規則に準ずる。ただし、Bクラブ、B3クラブ、Wリーグチーム、JSBF加盟・登録団体は、所属団体の規定に準ずる。
- ユニフォームの色
-
- 1. 組合せ番号が若いチーム (HOME) を淡色とする
- 2. ユニフォームの色を変更する場合は、両チームがともに淡色でないこと同色系以外であることとし、対戦する両チームで話し合い、お互い了承を得てから主管者の承認を受けること。
- 3. チームは濃色・淡色各ユニフォームを用意し、濃淡同番号とする。
- ベンチの位置
- 組合わせ番号の若いチームがテーブル・オフィシャルズに向かって右側とする(HOME側)
※ただし、両チームの了承のもと主管者の判断によりベンチ位置を変更することは、可能とする。
- ドーピング・コントーロール
- ドーピング・コントロール実施対象大会とする。
- その他
-
- (1) 提出書類に記載されたデータ (画像データ含む) は、主催者が大会運営のため大会プログラムや大会公式サイトなどに使用するほか、大会報道を目的として報道機関に提供することがある。試合中継等や大会に連動した事前・事後企画等での使用を目的として撮影された映像 (対象として選手・応援者個人の肖像や横断幕等の製作物等を含む) の全部またはその一部 (静止画を含む) は、場内での大型映像装置による放映をはじめ、公式メディア、テレビニュース、その他関連する現存または将来存在するであろうメディア等、 ならびに、大会主催者に指定された者 (パートナー企業を含む) により製作する映像作品をはじめとした各種の販売物等で使用される場合があるため、使用目的にかかわらず、これにつき予め無償にて同意したものとみなす。
- (2) 競技規則に則り、ゲーム開始予定時刻の15分を過ぎてもチームがコートにいない、もしくは、プレーをする準備の整ったプレーヤーが5人揃わなかった場合、ゲームの没収により当該チームは得点を0対20として敗戦扱いとする。但し、悪天候や地震等の天変地異、公共交通機関の不通や遅延、交通事情による道路の渋滞等、やむを得ない事由による場合、JBAはゲーム開始予定時刻の変更が可能である場合には両チームの合意なく、これを変更することができる。
- (3) 要項および大会関連書類に定めのない事項については、大会実施委員会で協議し、その指示に従うこと。